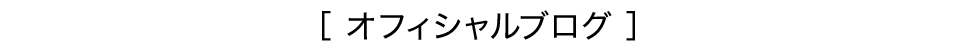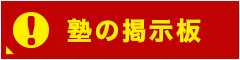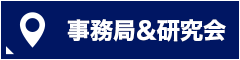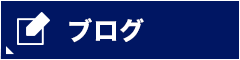「4技能入試」はなぜ頓挫したのか?
―共通テスト改革をめぐる現場の声と政治決着―
約10年前、日本の大学入試制度は大きな転換期を迎えていました。長年続いた「センター試験」から、思考力・判断力・表現力を問う「大学入学共通テスト」への移行が発表され、特に英語は「読む・聞く・話す・書く」の4技能評価を導入するという大改革が打ち出されました。
しかし――
実施目前の高2生を対象に、プレ共通テスト(試行調査)が行われたことで、想像もしなかった大騒動が起きたのです。
トップ校の高校生たちが立ち上がった!
このプレテストに強く反発したのが、東京の筑波大学附属駒場高校をはじめとする、全国のトップレベルの進学校の生徒たちでした。
彼らは口をそろえてこう訴えました。
「私たちは、こんなテストを受けるための教育を受けていない!」
これは単なるクレームではなく、署名運動へと発展し、数千人規模の署名が文部科学省に提出されました。高校生たち自らが陳情に赴き、直接声を届けたのです。
文科省の初期対応と“政治決着”
当初、文科省は「制度上の問題はない」として、この動きを退けていました。しかし、騒ぎは次第に大きくなり、教育界だけでなく、メディアや国会にも波及。ついに文部科学大臣が“政治決着”という形で折れざるを得なくなったのです。
その結果、4技能の全面導入は見送りとなり、現行の「リーディング+リスニング」の2技能体制が採用されました。
この出来事が私たちに示すもの
このエピソードは、日本の英語教育がいかに制度と現場の断絶の中にあるかを浮き彫りにしました。
・英語教育の現場は4技能に対応していなかった
・それなのに評価方法だけが先に変わろうとした
・現場の声が政策を動かした稀有な事例となった
つまり、教育改革はトップダウンだけでは進まないということを、あの高校生たちが身をもって示してくれたのです。
今、私たちは何をすべきか?
制度の変更だけでなく、「実際の授業・教材・学習法」こそが変わらなければ、本当の意味での改革にはなりません。
私たちは今こそ、
・「訳さずに英語を理解する」力
・「英語のリズムと語順」を体で感じ取る力
・「聞く・読む」から「話す・書く」への自然な発展
これらを育てる教育に舵を切るべきです。
「直聞&直読直解法」は、そのための一つの答えになるかもしれません。(つづく)
無料の入塾面接&授業体験を随時受け付けています
お子様の英語学習について、具体的なご相談やご質問がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。オンラインで全国どこからでもご対応いたします。
オンラインで全国どこからでもお問い合わせください!