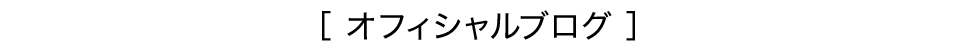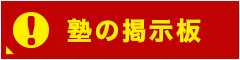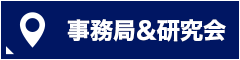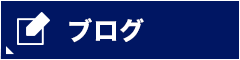第4話「英語のリズムには、2種類ある?」
(塾の帰り道、響はスマホにイヤホンをさして、アキ先生が薦めてくれた英語音声を聞きながら歩いていた)
英語音声(ナレーション)
“This is the reason why I decided to try a new method.”
響(心の声)
「…“This is the reason”のところ、すこし強め。“why I decided”は軽やかに流れて、“to try a new method”でまたしっかりリズムが戻る感じ…。
あれ?リズムの波がある? これって…何か法則があるのかも。」
(帰宅後、譜面のようにノートに例文を書きながら、響は自分で強く聞こえた語にアンダーラインを引いていった)
響(独り言)
「強く響く単語と、軽く流れる単語。これって、英語の“拍子”みたいなもの…?」
(翌日、塾でその話をアキ先生にする)
響
「先生、英語を聞いてたら、リズムに“2種類”あるような感じがしたんです。強く聞こえるところと、スーッと流れるところ…。音楽で言うと、強拍と弱拍みたいな…」
アキ先生(うれしそうに)
「その通り!英語のリズムは、内容語と機能語でできてる。内容語(名詞・動詞・形容詞など)は意味をもつから強く読まれやすくて、
機能語(冠詞、前置詞、代名詞など)は軽く、短く読まれる傾向があるんだ。」
響
「えっ、じゃあ英語のリズムって、“意味のある語”が主役で、“意味を支える語”は伴奏みたいなもの…?」
アキ先生
「うん。リズムの中でどこに意味の重みがあるかを感じとれるようになると、聞くのも読むのもスラスラできるようになる。
それが“語感”の第一歩なんだよ。」
響(感動しながら)
「そっか…。英語を“意味のかたまり”として、リズムで感じることができたら、きっと曲と同じで、一度聞いたら忘れないものになりそう…」
アキ先生
「いい気づきだね。リズムを意識しながら読む練習を始めてみようか?“意味の波”を感じる練習さ。」
響が感じとった「語のリズムの波」。
それは、直読直解の「意味のかたまりで読む力」につながっていく――(つづく)
※入塾を検討されている方は入塾面接をお申し込みになり、前もって「★入塾面接の栞」をお読みください。⇒事務局&研究会 | 武蔵ゼミナール (english634.com)
(※毎年7月中旬、期末テストが終わると《入塾面接予約》が集中して、入塾面接ができなくなります。お早めに入塾面接を済ませてくださるようお願いします。)
全国どこでも自宅でオンライン授業
★武蔵ゼミナール大学受験英語塾
https://www.english634.com