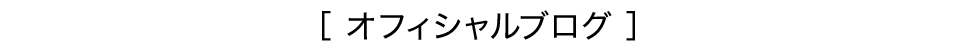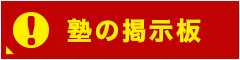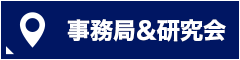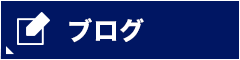第6話「ことばに宿るビート」
美術室の隣にある音楽室。
放課後の柔らかな日差しが、譜面台に並ぶ五線譜を照らしていた。
その日も、響は音楽室にこっそり立ち寄っていた。
机の上には英語のノートと電子辞書。そして隣には武蔵先生の書いたメモがある。
「tennis=2音節」「basketball=3音節」「photographer=4音節」
→英語の単語には“リズム”がある。
響(ひびき)は、思わず声に出してつぶやいた。
「te-nnis… bas-ket-ball… pho-to-gra-pher…」
その音節のリズムに合わせて、ピアノの鍵盤をぽん、ぽん、と指で叩く。
音が言葉と連動する。まるで、英語が音楽になったようだった。
そのとき、背後から声がした。
「リズムに気づいたようだね、響ちゃん」
振り返ると、アキ先生——いや、武蔵先生が立っていた。
どうやら様子を見に来てくれたらしい。
響「はい。英語の単語って、長さが違うんですね。
ピアノみたいに、短い音と長い音が混ざってる。
なんか…しゃべる音楽みたいです」
武蔵先生「まさにその通り。英語の“語感”っていうのはね、音節のビート感に気づくところから始まるんだよ。
それがあると、聞き取れるし、伝えられるし、読んでいてもリズムでわかってくる」
先生は、黒板に3つの単語を書いた。
photo-graph(3音節)
pho-to-gra-pher(4音節)
pho-to-gra-phic(4音節)
武蔵先生「どれも“photo”から始まっている。でも、リズムが違う。
そのリズムの変化に“意味のヒント”が隠れているんだ。たとえばね——」
そして続けて書いたのは例文。
This is a photograph of my grandfather.
She’s a professional photographer.
I love photographic art.
響「うわ、ぜんぶ“photo”で始まってるのに、意味が全然違う…」
武蔵先生「だから大切なのは、意味じゃなくてまず“音”。
音節リズムの違いが、役割の違いに直結している。
語尾が変わることで、英語は“品詞”も“役割”もリズムで変えるんだ」
響「すごい…リズムの魔法みたいですね。
音が違えば、意味も変わってくるってことなんですね」
響は目を輝かせて、ピアノの鍵盤をそっと叩いた。
「pho-to-gra-pher… 4つの音節、4つのビート…」
その瞬間、彼女の中で“英語”という言葉が、またひとつ“音楽”に近づいた。
——“ことば”は“音”でできている。
そして“音”は、“リズム”を運ぶ。
彼女の中に、確かに新しい英語の世界が生まれていた。
(つづく)
※入塾を検討されている方は入塾面接をお申し込みになり、前もって「★入塾面接の栞」をお読みください。⇒事務局&研究会 | 武蔵ゼミナール (english634.com)
(※毎年7月中旬、期末テストが終わると《入塾面接予約》が集中して、入塾面接ができなくなります。お早めに入塾面接を済ませてくださるようお願いします。)
全国どこでも自宅でオンライン授業
★武蔵ゼミナール大学受験英語塾
https://www.english634.com