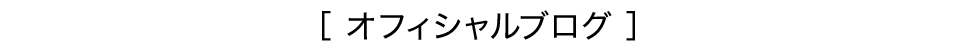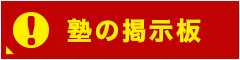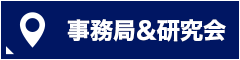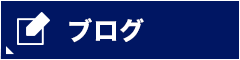第12話「音節リズムと内容語リズム」
英語のリズムには、ふたつの“秘密”があるらしい。
ひとつは、「音節リズム」
もうひとつは、「内容語リズム」
そう翔太は言った。
「響は、日本語の『ミルク』って、何拍で言ってるか分かる?」
「え? ミ・ル・ク、で、3拍?」
「そう。日本語は“拍”の言語なんだ。だけど、英語は違う。英語は“音節”の言語」
「ミルクって、英語だと…milk。たった1音節だ…!」
翔太は続けた。
「『バスケットボール』は日本語で7拍。でも英語じゃbasketball、たった3音節」
響の目がみるみる真剣になっていく。
「このリズムの違いが、英語が通じない最大の理由なんだよ。音が違うんじゃなくて、リズムが狂ってる」
「……たしかに。メロディーが同じでもリズムが狂ってたら、曲として崩れるもんね」
英語の通じなさは、まるで“リズムのずれた演奏”のようだった。
───
「そしてもう一つが『内容語リズム』。英語では、名詞や動詞など**“意味のある言葉”**だけを強く言う」
「意味のある言葉……じゃあ、逆に弱く言うのは?」
「前置詞、冠詞、代名詞、be動詞、助動詞……つまり“文法を支える言葉”は弱く短く」
響は、ショパンの楽譜を思い出す。
強く響かせる音と、添えるような音──
ピアノの表現と、まったく同じじゃないか。
「英語は、内容語を一定の間隔で打つビートみたいなもの。それに文の“骨格”が添えられて、流れが生まれるんだ」
───
夜。
響は英語のフレーズをリズムに乗せて口ずさんでみた。
“This is the reason why I decided to try a new method.”
強く読むのは──
“This” “reason” “decided” “try” “new” “method”
まるでピアノのアクセント記号のように、浮かび上がってくる。
英語って、
ただの言語じゃない。
リズム。ビート。強弱。
まるで音楽だ──
───
次の日。
響はジャズチャンツの英語を、ピアノの前で「読む」のではなく、「弾くように」発音していた。
「英語って、やっぱり音楽だよ。読むんじゃない。演奏するんだ…!」(つづく)
※入塾を検討されている方は入塾面接をお申し込みになり、前もって「★入塾面接の栞」をお読みください。⇒事務局&研究会 | 武蔵ゼミナール (english634.com)
(※毎年7月中旬、期末テストが終わると《入塾面接予約》が集中して、入塾面接ができなくなります。お早めに入塾面接を済ませてくださるようお願いします。)
全国どこでも自宅でオンライン授業
★武蔵ゼミナール大学受験英語塾
https://www.english634.com