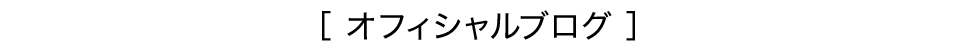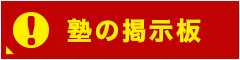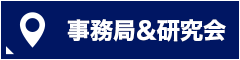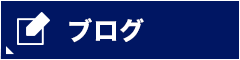登場人物
響(ひびき):高3女子、ピアノ専攻の音大志望。リスニングが苦手。
アキ先生:武蔵ゼミナール大学受験英語塾の塾長。音と語感を重視する教え方。
第1話「音が分かるって、どういうこと?」
模試の結果が返ってきた。
リスニング32点、100点満点のうち、まさかの半分以下。
予想はしていたけど、あまりにも低かった。
響(ひびき)は、音楽予備校のロビーの隅で、答案用紙を見つめたまま固まっていた。
「聞こえてるのに、意味が浮かばない……」
問題の英文は、確かに耳に入っていた。けれど、その「音」はただ流れ去るだけで、意味がついてこなかった。
音符を追いながら、どの調なのかまったくつかめないような感覚。
――英語は、楽譜じゃなかった。
ピアノを10年以上弾いてきた響にとって、「音がわかる」という感覚はとても身近なものだった。
でも、「英語の音」は、それとはまるで違っていた。
「英語って、音でできてるって言うけど……音が“わかる”って、どういうこと?」
イヤホンを外し、バッグにしまいながら、響はため息をついた。
駅までの帰り道。ふと目に入った一枚の看板に、足が止まる。
> 「武蔵ゼミナール 英語専門塾」
> ――英語を“音”から学ぶ、という選択。
「音から……?」
その言葉に、なぜか心が引っかかった。
数日後。体験授業の予約を入れた響は、武蔵ゼミナールの小さな教室に座っていた。
前に立つのは、アキ先生。落ち着いた雰囲気で、だが目の奥に強い意志を感じる人だった。
「英語が“わかる”って、どういうことだと思いますか?」
最初の一言で、教室の空気が変わった。
「多くの人は、“英語を見て理解する”ことを重視します。でも、人間はもともと――音で言葉を覚える生き物なんです」
響は、思わず顔を上げた。
「脳の研究では、耳は目よりも早く進化したとわかっています。
赤ちゃんは、見える前から“母親の声”を聞いて育つ。
言葉の意味も、文字じゃなくて“音”のくり返しで覚えるんです」
響の脳裏に、幼い頃、母の歌う子守唄がよみがえった。
言葉じゃなくて、音の記憶。それは、確かに響の中にあった。
「英語も同じです。音に意味が乗っている。
目で読むだけでは、そのリズムや抑揚、語感は身につかない。
だから私たちは、“直聞直解”で教えています。――音を聞いて、意味をつかむ。訳さないで、感じる」
その言葉が、心に染み込んだ。
休憩時間。響はバッグからスマホを取り出し、アプリを開いた。
さっき教材で使った例文を、もう一度聞いてみる。
“This is the reason why I decided to try a new method.”
流れる英語の音。いつもならただのBGMのように感じていたのに、今日は少し違って聞こえた。
ゆっくりとリズムを感じながら、響はつぶやく。
「This is the… reason why I… decided to try a… new method…」
まるでピアノのフレーズを練習しているみたいだった。
ひとつひとつの音に、意味が乗って流れていく――そんな感覚。
「……あれ? なんか、ちょっとだけ“わかる”かも」
夕焼けの街を歩きながら、響は空を見上げた。
少しだけ軽くなった気持ちと、胸の奥に芽生えた小さな好奇心。
「音がわかるって、意味を“あとづけ”することじゃないのかも」
「音を聞いたとき、自然に意味が浮かぶ……そんな英語、私も感じてみたい」
ピアノのように。旋律を奏でるように。
英語にも、きっと“音楽”がある。
そしてその音楽を、彼女はまだ知らないだけだった。(つづく)
― 響と英語のリズムが出会うとき ―
音楽を愛する人は、音の中に意味を聴きとります。
そして英語もまた、音の言葉――リズムと抑揚のある「生きた音声」です。
この物語の主人公・響(ひびき)は、音大を目指す女子高生。
ピアノの鍵盤に向かうとき、彼女の耳と心は音楽の流れに寄り添います。
そんな彼女が出会ったのは、「英語も音楽のように読める」というまったく新しい学び方。
それが「直聞直解法」そして「直読直解法」でした。
英語の音節リズム、内容語リズム、抑揚のパターン――
これらは決して文法書の中だけの知識ではなく、実際の会話やリスニングの「命」です。
響の目を通して、
英語が「文法や単語の暗記」ではなく、「音の芸術」として立ち上がってくる瞬間を、
ぜひ皆さんも体験してみてください。
※入塾を検討されている方は入塾面接をお申し込みになり、前もって「★入塾面接の栞」をお読みください。⇒事務局&研究会 | 武蔵ゼミナール (english634.com)
(※毎年7月中旬、期末テストが終わると《入塾面接予約》が集中して、入塾面接ができなくなります。お早めに入塾面接を済ませてくださるようお願いします。)
全国どこでも自宅でオンライン授業
★武蔵ゼミナール大学受験英語塾
https://www.english634.com